小学生のころ、河原の石や、道ばたに落ちているなんでもない石をひろい集めていたことがありました。
灰色の石の表面に白くまっすぐなスジが入っているとか、キラキラ光る小さな石英の結晶が見えるとか、そんなちょっとしたことが、ものすごく貴重なもののように思えて、たまに金色に光る黄銅鉱のまざった石でも見つけようものなら、本物の黄金でも見つけたようにワクワクしたものでした。
大人になると、石に対するそうしたワクワク感は消えてしまいましたが、「ミステリーストーン」(筑摩書房刊)という本には、大人になっても石への情熱を持ち続け、永遠に石に魅せられてしまった人たちの、ちょっとふしぎな話しが書かれています。
禿(は)げ山でトパーズを掘り当て、よろこびのあまり雪の降りしきるなか、ひとり舞い踊る人の話し、宮沢賢治の「石ぐるい」のこと、石にまつわる世界の伝説のほか、石についての奇妙な話しがいっぱいです。
そのひとつに「蛇頂石(じゃちょうせき)」という名のふしぎな石の話しがあります。
昭和のはじめ、京都の鳩居堂で実際に販売されていたものらしく、効能書の写真まで載せてあるのですが、それは小さな黒い楕(だ)円形の石で、ムカデなどにかまれたところにペタッとはりつけると、痛みが消え、毒を吸い出してくれるということです。
使った後に水に入れておくと「プクプクとかわいらしい小さな泡(あわ)が出て~毒をはき出し」、石をふいてしまっておけば、また使えるという「魔法の石」だそうです。
こんなの今でも売ってたら、私は買いますけどね。

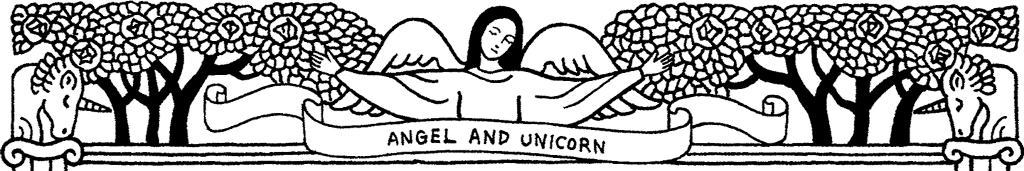
高校生の頃、「蛇紋岩」というのが流行りました。
或る地域の学友が「これ、知っているか」と学校に持ってきたのが始まりで、爾後「俺にも持ってきてくれ」という生徒が続出したのです。
つたない記憶をたどると、彫刻などしたように思います。
「もろい石だなー」とも思ったようです。